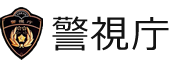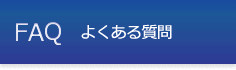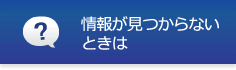更新日:2016年7月4日
防犯環境設計とは、犯罪が発生しにくい環境を創るために、人的な防犯活動(ソフト面)とあわせて、建物、道路、公園等の物理的な環境(ハード面)の整備、強化等を行い、犯罪の起きにくい環境を形成するという考え方をいいます。
防犯環境設計には、直接的な手法として「対象物の強化」と「接近の制御」、間接的な手法として「監視性の確保」、「領域性の確保」があり、これらを総合的に組み合わせることが重要です。
防犯環境設計における4つの要素
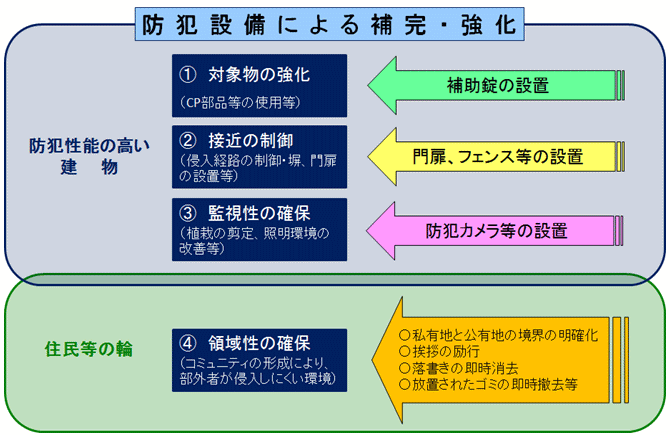
対象物の強化
「対象物の強化」とは、丈夫な錠や防犯ガラスなどで対象物を破壊に強く物理的に強化して侵入を未然に防ぐことです。
補助錠を取り付ける
玄関ドア、サッシ等には補助錠等を取付け補完する。
防犯フィルムを貼付する
ウィンドウフィルムを窓ガラス前面に貼付し防犯効果を高める
専門の施工業者に貼付してもらうのが効果的です。
防犯性能の高い建物部品(CP部品)に交換しましょう。
防犯性能の高い建物部品(CP部品)は、警察庁等関係省庁と民間団体が結成した「官民合同会議」において、工具等を使用した試験を実施し、一定の防犯性能があると認定された建物部品(ドア・ガラス・サッシ・錠・シャッター、面格子、ウィドウフィルム等)です。

接近の制御
「接近の制御」とは、境界を作って人が容易に敷地や建物に接近することを防ぐことです。
境界への塀、柵の設置
道路と敷地の境界線を明確にし、門扉、フェンス等で侵入禁止の意思表示をする。
共用出入口、駐車場の制限
オートロックシステムなどで居住者に限定した出入制限をし、他人の侵入を未然に防止する。
足場になるような物の除去
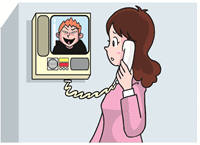
脚立やポリバケツ等、足場になる可能性のあるものは置かない。
監視性の確保
「監視性の確保」とは、街路や窓からの見通しを確保し照明機器を改善し、人の目が周囲に行き届くような環境をつくり侵入を未然に防止することです。
照明環境の整備
夜間等人の出入りを感知するセンサー付きライト等を設置する。
周囲の見通しを確保
植木等は剪定し、屋内から外周が外周から敷地内が見通せる環境にする。
防犯カメラ等の設置
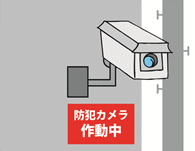
プライバシー等の問題を考慮し、適正な使用方法を遵守し防犯カメラを設置する。
領域性の確保
「領域性の確保」とは、住宅やその周辺の維持管理状況を改善したり、住民相互の活動や交流を促して部外者が侵入しにくい雰囲気を地域で形成することです。
物理的・心的障壁による領域の明示
侵入者は絶対に許さないという毅然とした態度を示す。
コミュニティ活動の促進
平素からご近所同士であいさつ、声掛けを励行し交流を深め、地域を明るくする協同した活動を実施する。
帰属意識の醸成
自分の住んでいる街を知り、愛して、見知らぬ人には積極的に声掛けするなど一人ひとりが「地域の目」で犯罪の起きにくい街を創っていく。
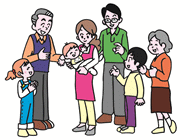
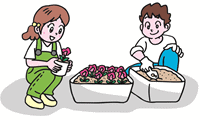
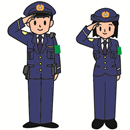
情報発信元
警視庁 生活安全総務課 個別防犯係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)