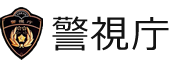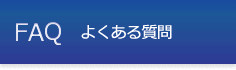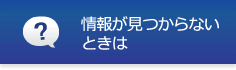更新日:2019年8月1日
![]()
暖かくなってくると、子ども達の行動範囲もぐっと広がってきます。
子ども達は、保護者の目の届かないところで、どのような行動をとっているのでしょう。
この機会に、子どもの行動やその範囲を確認してみましょう。
子どもの交通事故の特徴
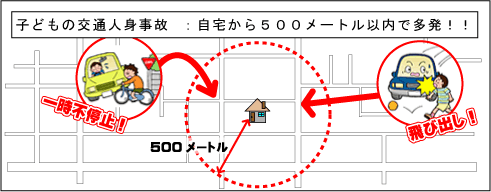

子どもの交通人身事故で多いのは、
- 道路横断中
- 自宅付近
- 夕方の時間帯
- 自転車の事故
- 小学生の男子児童
自転車では、交差点での安全確認が不十分なことや一時停止しなかったことが原因になっています。また、歩行中では飛び出しが原因になることが多くなっています。
- 詳しい事故状況・統計については、
で見ることができます。
子どもの交通事故事例
![]()
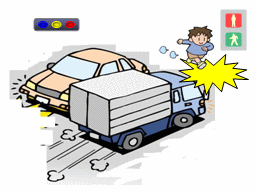
信号に従っていても、横断歩道を渡っていても、必ずしも安全ではありません。
右折や左折をする車、信号の変わり目で無理矢理交差点に進入してくる車、横断中の歩行者に気がついていない車などがあるかもしれません。必ず、右左(みぎひだり)の安全確認をして、車が止まっているか、運転手さんが自分に気がついているかなどを確認してから渡りましょう。
小学生の交通事故
信号機設置・交差点・横断歩道を横断中
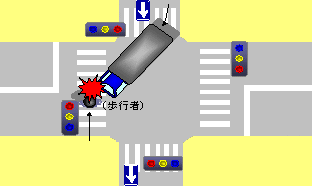
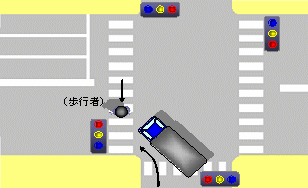
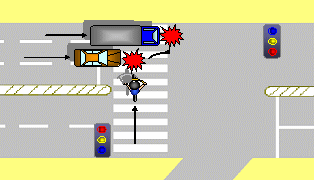
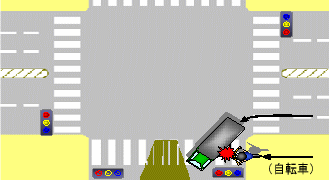
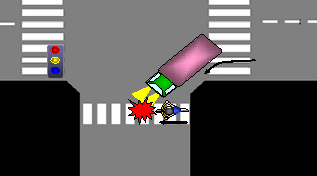
(注記)道路形状等一部異なる場合があります。すべての交通規制や信号機を表示しているものではありません。
幼児の交通事故
子どもはお母さんの後を追います。注意!
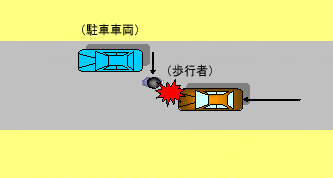
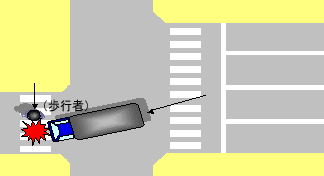
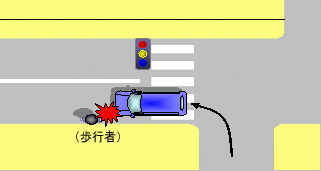
(注記)道路形状等一部異なる場合があります。すべての交通規制や信号機を表示しているものではありません。
幼児の事故では、保護者と一緒に道路を渡ろうとして、保護者の後を追いかけて車にひかれて亡くなったという悔やみきれない交通事故が発生しています。
買い物の途中、幼稚園の送迎時、帰宅時に幼児を降車させた直後などは、幼児から目を離さないでください。
保護者の皆さんへ
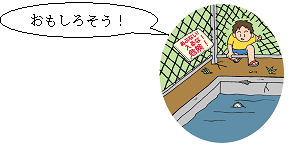
子どもは興味があると、そのことに夢中になって、周囲の状況が目に入らなくなり、危険なことの判断ができなくなります。
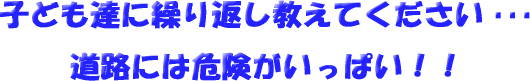
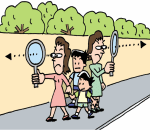
新入学、新学期に向けて、交通安全について子どもと一緒に考えましょう!
通学路だけでなく、塾や遊びのために利用する道路に潜む危険を子どもの目線で見てください。
子どもの視界を体験できる「チャイルドビジョン(幼児視界体験メガネ)」の活用も効果的です。
歩く時の約束

- 道路を渡るときは横断歩道を渡りましょう。
- 信号が赤の時はとまり、青の時は右と左をよく見て、車が来ていないかを確かめてから渡りましょう。
- 道路を横断中も、右と左をよく見て、車が来ていないかを確かめましょう。
- 道路や車のそばでは、絶対に遊ばないようにしましょう。
- 道路には飛び出さないようにしましょう。
自転車に乗る時の約束
1. 自転車は、車道通行が原則です。
子ども(13歳未満)が自転車に乗るときは、歩道を走ることができます。

(注記)大人(13歳以上)が自転車で歩道を通れるのは、標識などがある場合と車道を通るのが危険な場合です。
ただし、70歳以上の人と身体の不自由な人も、子どもと同じように歩道を通ることができます。
2. 歩道では、車道寄りをゆっくり進みましょう。
(注記)歩行者が多いときは、自転車からおりて、おして歩きましょう。
3. 交通ルールを守りましょう。
自分、そして他の人を守るために
- 二人乗りをしてはいけません。
- 自転車でならんで走ることはやめましょう。
- まわりが暗くなったら、かならずライトをつけましょう。
- 信号を守りましょう。
- 下記標識があるところは一度とまって右と左の安全を確認しましょう。


4. ヘルメットをしっかりかぶりましょう。
保護責任者は、小学生・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めましょう。
車に同乗中の事故防止

車に同乗中の交通事故で、車外に投げ出されるなどの被害にあわないために車に乗るときは、必ずシートベルト・チャイルドシートをしましょう。
後部座席のシートベルト着用も義務化されています。運転をする方は、取締りを受けるからでなく、同乗者の命を預かっているという意識を持ってください。
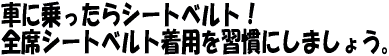
小さいうちから、具体的に道路での危険な行動や交通ルール・マナーについて繰り返し教え、大人の真似ではなく、自分自身で危険なことの判断や、なぜ交通ルールやマナーを守ることが大切なのかを理解させ、「自分の命は自分で守る」ことを身に付けさせましょう。
「具体的に」とは?
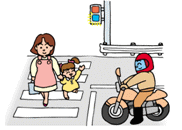
小さい子どもは、抽象的な言葉「危ない」「注意しなさい」では理解できません。
具体的に「なぜ危ないのか」「どう注意したらよいか」を教えましょう。
それには、実際利用する道路で歩道の歩き方や横断の仕方を教えながら、同時に歩行者とは違う動きをする車やバイクについても教えましょう。(例:合図、右左折など)
交通安全教育や講習会について
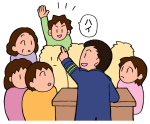
免許のある方でも、歩行者や自転車の交通ルールについてはよくわからないという方が多いのではないでしょうか?
お近くの警察署や区市町村では、春・秋の交通安全運動の一環として、また、それ以外の時期にも学校・PTAなどの要請で対象別に各種交通安全教室等を行っています。

子どもを対象とした学校や地域での交通安全教室では、歩行訓練・自転車実技訓練なども行っています。
保護者自身も子どもに正しく教えるために、積極的に交通安全教室や講習会に参加していきましょう!
警視庁安全教育センターで実施している安全教室はイベントページから確認してください。
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全対策第一係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)