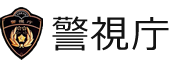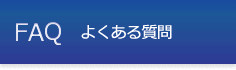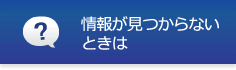更新日:2025年6月23日
安全運転管理者等講習について
令和7年度安全運転管理者等講習について
- 講習は、受講に際し事前に手数料を納入した上で、お申し込みしていただきます。
- 「オンライン講習」と「会場講習」を選択することができますが、可能な方はオンライン講習の受講にご協力をお願いします。
- 安全運転管理者・副安全運転管理者の皆さまには、日程や申し込み方法等について封書にてご案内します。
- お申し込みをしていない方の受講はできません。
- 会場での現金での手数料の徴収はいたしませんのでご注意ください。
![]() 安全運転管理者講習の申込み・受講方法について(PDF形式:607KB)
安全運転管理者講習の申込み・受講方法について(PDF形式:607KB)
日程や申し込み方法等はこちらからご覧いただけます。
よくあるQ&A
![]() 安全運転管理者等に関するよくある質問(PDF形式:282KB)
安全運転管理者等に関するよくある質問(PDF形式:282KB)
安全運転管理者等の選任義務
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
(道路交通法第74条の3第1項、第4項)
安全運転管理者等の選任
安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1名を選任する。
- 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。
- 業務で使用する車両を台数として計算。
副安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の11)
副安全運転管理者の人数は、自動車の台数によって異なります。
選任を必要とする自動車の台数は20台以上とし、20台毎に1人の追加選任が必要となります。
| 自動車の台数 | 副安全運転管理者 |
|---|---|
| 19台まで | 不要 |
| 20台から39台まで | 1人 |
| 40台から59台まで | 2人 |
| 20台ごとに1人の追加選任 | |
罰則
- 安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合は「50万円以下の罰金」
(法人等両罰50万円以下の罰金)
- 選任の届出をしていなかった場合は、「5万円以下の罰金」
(法人等両罰5万円以下の罰金)
![]() 東京都内の安全運転管理者選任事業所一覧(2025年1月20日現在)(PDF形式:3,372KB)
東京都内の安全運転管理者選任事業所一覧(2025年1月20日現在)(PDF形式:3,372KB)
安全運転管理者等の資格要件
安全運転管理者、副安全運転管理者の選出に当たっては、以下の要件を満たす方を選任してください。
安全運転管理者
年齢20歳(副安全運転管理者が選任しなければならない場合は30歳)以上の方
副安全運転管理者
年齢20歳以上の方
上記資格要件を満たしていても、次に該当する方は安全運転管理者等にはなれません。
過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令(道路交通法第74条の3)を受けた者
以下のいずれかの違反をした日から2年を経過していない者
- ひき逃げ
- 無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転
- 無免許運転にかかわる車両の提供・無免許運転車両への同乗
- 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類を提供する行為
- 酒酔い・酒気帯び運転車両への同乗
- 次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反 - 自動車使用制限命令違反
- 妨害運転に係る罪
安全運転管理者等の選任(解任)届、変更手続き(道路交通法第74条の3第5項)
自動車の使用者は、安全運転管理者等の選任・変更日から15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届け出てください。
届出方法は、警察署窓口・警察署へ郵送・警察行政サイトがあります。
安全運転管理者・副安全運転管理者の選任・変更(4種類提出)
- 届出書(安全(副安全)運転管理者に関する届出書)
- 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
- 運転免許証の写し
- 運転記録証明書(3年間若しくは5年間のもの)
(注記1)「3」「4」は運転免許証保持者
(注記2)運転記録証明は、自動車安全運転センターで発行しています。
記載事項の変更(届出書のみ提出)
事業所名、所在地、安全運転管理者等の氏名、職務上の地位、自動車の台数に変更を生じたとき等
安全運転管理者・副安全運転管理者の解任(届出書のみ提出)
自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が別の警察所管内に移転、又は事業所が閉鎖することになったとき等
詳しくは、事業所の所在地を管轄する警察署交通課もしくは警視庁交通部交通総務課交通安全組織係までお問い合わせください。
安全運転管理者等の解任
解任には、次のような場合があります。
- 自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が別の警察署管内に移転、又は事業所が閉鎖することになったとき等。
- 安全運転管理者等が前記「安全運転管理者の選任の資格要件」を備えなくなったときのほか、交通安全教育指針に基づく職場の交通安全教育を怠ったため、自動車の安全運転が確保されていないと認めるとき公安委員会は、自動車の使用者に対し、安全運転管理者等の解任を命ずることができます(解任命令)。
なお、公安委員会が解任を命じようとする場合は、弁明及び有利な証拠の提出の機会が与えられます。
安全運転管理者の業務
安全運転管理者は、その管理下の運転手に対して、国家公安委員会が作成・公表する「交通安全教育指針」に従った安全運転教育や、内閣府令で定める安全運転管理業務を行わなければなりません。(道路交通法第74条の3第2項、第3項)
内閣府令で定める安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
(1)運転者の適正等の把握
自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。
(2)運行計画の作成
運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。
(3)交替運転者の配置
長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。
(4)異常気象時等の措置
異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。
(5)点呼と日常点検
運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(6)酒気帯びの有無の確認
運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて、確認を行うこと。
(7)酒気帯びの有無の確認の記録保存・アルコール検知器の常時有効保持
酒気帯びの有無の確認内容を記録し、一年間保存するとともに、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
(8)運転日誌の備付け
運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
(9)安全運転指導
運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
安全運転管理者は、使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。前述した規定の事項は安全運転管理業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。
安全運転管理者等講習(毎年1回)
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受けさせなければなりません。(道路交通法第74条の3第8項)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
警視庁 交通総務課 交通安全組織係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)