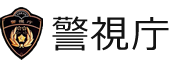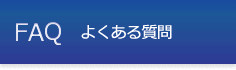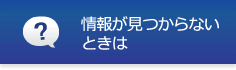更新日:2025年6月20日
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)が平成23年6月24日に公布され、改正法により、刑法に新たに「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪」)」が設けられ、同年7月14日に施行されました。

この法律により、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられることになりました。
コンピュータ・ウイルスに感染してしまうと、パソコンの中に保存してある個人情報や重要なデータが流出してしまったり、パソコンが壊れてしまうおそれがあります。
インターネットを利用している方は、コンピュータ・ウイルスに対する自己防衛を行い、被害を未然に防止しましょう。
この法律では、以下の電磁的記録、その他の記録を処罰の対象としています。
- 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
- 上記に掲げるもののほか、上記の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
ウイルス作成・提供罪とは
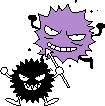
正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのプログラム(ソースコード)を作成、提供する行為をいいます。
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が課せられます。
ウイルス供用罪とは
- 正当な理由がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合や、その状態にしようとした行為をいいます。
- 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が課せられます。
ウイルスの取得・保管罪とは
- 正当な理由がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為をいいます。
- 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が課せられます。
ウイルスに感染してしまったら
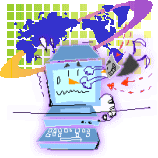
- 被害の拡大を防止するため、ネットワークから切り離す
- 最新のパターンファイルが適用されているウイルス対策ソフトにより、コンピュータ内の検索とコンピュータ・ウイルスの駆除を行う
- 駆除ができない場合は、利用しているウイルス対策ソフトの会社のホームページなどで、コンピュータ・ウイルス名を元に対処方法を探す
- 可能であれば、パソコンの初期化を行うのが望ましい
サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口
サイバー事案に関する通報・相談・情報提供のオンライン受付窓口、サイバー犯罪に関する電話相談窓口についてご案内しています。
情報発信元
警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)