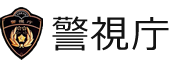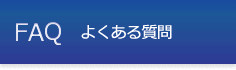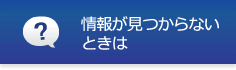更新日:2024年7月4日
情報の拡散
従来、うわさや情報は、直接会って広まるものでしたが、インターネットの普及によってより簡単に広まるようになりました。例えば、インターネット拡大初期にはチェーンメールが生まれ、さらに今ではSNSやメッセージアプリでの拡散が行われるようになっています。
インターネット上で広まる情報には様々なものがありますが、本当のことか疑わしい例として、
- ○月×日△時ごろに関東で大地震が発生すると発表がありました
- 有名企業○○が実は倒産寸前らしい
- △△駅に通り魔発生!今すぐ逃げろ!
- 新しい犯罪手口が流行っているので、このような対処をしてほしい
- 地震の影響で、動物園からライオンが逃げ出した
- 新型ウイルスの問題で、現在品薄のマスクを無料送付
- マスクと同じ原料のため紙製品(トイレットペーパー等)が品薄に、海外からも輸入できなくなる
などといった内容が、もっともらしく書かれており、つい信じてしまいそうになります。
しかし、これらの情報は本当のことなのでしょうか?
インターネット上で流れる情報は全て真実とは限らない

得られた情報が自分や友人に影響のある内容の場合、急いで教えたくなりますが、まず、その情報が本当か確かめる必要があります。何故なら、インターネット上で流れる情報は全て真実とは限らないからです。
もしウソや根拠のない情報を拡散してしまった場合、
- 自分の信頼が損なわれる
- (信じて拡散してしまった場合)友人の信頼も損なわれる
- 風説の流布や犯罪にあたる場合がある
- 風評被害が広まったとして企業等に損害賠償を請求される
等、不利益を被る可能性があります。このような事態にならないよう、落ち着いて情報の真偽を自ら判断しましょう。
疑わしい情報を判断するヒント
インターネットに慣れている人でも、疑わしい情報を信じてしまう人は少なくありません。情報に以下のような書き方が含まれている場合は、特に注意して、情報源を確認してから伝えるようにしましょう。
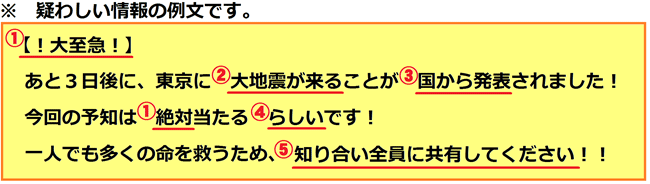
強調表現、不安をあおる表現や急がせる表現が多い
その情報が本当であれば、事実のみを記載すれば十分です。しかしウソの情報は、強調表現や不安をあおる表現で信じ込ませ、急いで拡散させようとします。
デマに含まれやすい表現の例
- 強調表現 非常に、かなり、すごく、絶対、全て、必ず、重大な等
- 不安をあおる表現 危険な、悪質な、大変な等
- 急がせる表現 即、大至急等
生命や金銭に関わる内容
避難情報や災害情報等、生命に関わる内容も多く悪用されます。また、「無料だったサービスが来月から有料になる」「有料サービスが期間限定で無料になる」等、金銭に関わるものも悪用されやすいので、必ず情報源を確認しましょう。
情報源が記載されていない
本当のように記載されていても、リンク(情報源のURL)や根拠が記載されていない場合は、必ず自分で検索して情報源を確かめましょう。官公庁や企業に関するものであれば、公式ホームページや公式ブログ等を確認してください。
また気象情報など、内容によってはテレビやラジオ等を確認することも有効です。
伝聞形式で書かれている
記載されている情報に、「らしい」「みたい」「だそうです」等の伝聞形式が含まれている場合も注意が必要です。「友人が」「知り合いが」「芸能人が」など情報源があいまいな場合は、当事者と直接話をしたり、公式ホームページを検索するなどして確認するようにしてください。
拡散を勧めている
拡散を勧める書き方には、大きく分けて、悪意によるものと善意によるものの2パターンがあります。どちらであっても、情報源を確かめ、無闇に拡散しないことが重要です。
悪意ある拡散の要求の例
- 「見てから○時間以内に×人に回さないと不幸になります」
- 「この情報を止めた人は特定され、襲われます(捕まります)」等
善意による拡散の要求の例
- 「ペットショップがつぶれたので、もらってくれそうな人に広めてください」
- 「被害を未然に防ぐために、知り合い全員に共有してください」等
その他、特殊な場合として、情報源そのものが虚偽であるサイト(いわゆるジョークサイト)であることがあります。常識的にありえない内容でも、信じてしまう人もいます。もし皆さんがこのような情報を受け取った場合は、情報の真偽を確認する習慣をつけましょう。
サイバー事案に関する通報・相談・情報提供窓口
サイバー事案に関する通報・相談・情報提供のオンライン受付窓口、サイバー犯罪に関する電話相談窓口についてご案内しています。
情報発信元
警視庁 サイバー犯罪対策課 対策係
電話:03-3581-4321(警視庁代表)